鈴久の告白記、第三弾です。
ここから、鈴久の成功にいよいよ弾みがつきます。相場で儲けるだけでなく、買い集めた株の力で経営改革や企業乗っ取り、企業合併など、縦横無尽に暴れ回ります。
明治四十二年五月号p94-97「余が失敗時代の回顧と楽天主義」
同六月号p6-12「嘗て余が一千万円を勝ち得たる経路」 ← 前回掲載
同七月号p45-52「古今未曽有と称せられたる予が全盛当時の活劇」 ←今回掲載
その他の情報は最後に置きました。
============================
− 「ブロマガ」サービス終了にともない、ブログを移転しました。この記事は、もとは 2014年8月20日に公開されたものです。
− なるべく原文のままとして、最小限の現代語訳を施した。
−(マルカッコ)は原文のまま。または、原文にあるフリガナを収めた。
−〔四角いカッコ〕は、訳者による補足。
− 原文で判読できない文字は□とした。
============================
実業之世界 第六巻第七号 (鈴久の半生涯)
『古今未曾有と言われた私の全盛当時の活劇』
――前号所載『かつて私が一千万円を勝ち取った経路』の続き――
鈴木久五郎
▼機関仲買店の開設
私は〔明治〕三十七〔1904〕年の十一月四日、洋行へと出発したが、途中で上海に立ち寄り、日露戦争がいよいよ危機に迫ったのを見て心機一転し、ただちに帰国して兄と談合のうえ、百万円を賭して株式界に輸贏〔しゅえい=勝ち負け〕を争った。ところが、屈辱的講和に対する国民の余憤〔収まらない怒り〕が凝り固まって日比谷公園の焼き討ちとなり、天下は騒然となり、株式は暴落に暴落をかさね、それに加えて鈴木銀行の取り付け騒ぎが起こったが、馬場金助氏らの義俠によって、ようやく難関を切り抜ける。すると今度は私自身が腸チフスに罹り、順天堂医院に入院した。この経緯と、その間に処した惨憺たる苦心とは、すでに前号において述べた。
さてここからは、私の得意時代である。
私は病院から出て考えた。他人の店に株の注文をするのは不得策である。安く買えるものを高く買わされたり、高く売れるものを安く売らされたりする。これに加えて、自分が頼んだ株を正式に取引所へ取り次いでいるのか、あるいは『呑んで』いるのか、すこぶる疑わしい〔呑む=仲買店が、顧客の売買注文を受け付けておきながら、実際には売買しないこと〕。五百株や千株ならどうでもよいが、何万もの株にもし間違いが起ころうものなら、こちらの存廃存亡にかかわる。そこで、自分で店を拵〔こしら〕える必要を感じた。
それなら誰に店をやらせればよろしいか。思い当たったのは、瀧沢吉三郎〔たきざわ きちざぶろう〕君である。高等商業の出身で、高橋義雄〔三越の経営などにあたった実業家、茶人〕の乾兒〔こぶん〕として、かつて三井銀行にあり、それから大阪住友銀行の副支配人となり、さらに抜擢されて東京支店支配人となって今日にいたる。交際してみると、ちょっと人格もあるし、とりわけ長く銀行業に従事している人だから金融界の事情に詳しい。
瀧沢君はチョイチョイ遊びにくる。まず私が何気なく、「どうです面白い事はありませんか」と聞くと、「月給取りほど馬鹿らしいものはない」と前置きして、「自分の理想は、もともと株式業者になることであった。欧米の仲買業者と連絡して日本の公債や株式を欧米市場に売り出すことであった。半田庸太郎〔東京の相場師。隻眼で独眼龍将軍とも呼ばれた〕の妹を娶り、しばらく半田の店の手伝いをしていたのも、この理想を実施しようとしたためであった。ところが不幸にして、事実は理想と異なり、三井銀行に入って住友銀行に転じ、四十一歳の今日まで、いまだ月給取りの境遇を脱し得ないのは、我ながらあまりに意気地のないことだ」と、瀧沢君は述懐した。
私は、この機に乗ずべしと思い、「それなら私が金を出すから仲買をおやりなさい。私も単純な考えで相場をしているのではない。後々にはこういう考えを持っているのだ」といろいろ自分の抱負を語り、住友銀行を辞職することを勧めた。すると瀧沢君は、「二、三日考えさせて貰う」と言って帰ったが、ふたたびやってきて、「いよいよ辞職を決心した」と言って、ただちに大阪へ辞職の談判に行った。そうして住友吉左衛門〔すみとも きちざえもん、住友財閥当主が代々襲名する名前。このときは十五代目の住友友純=すみとも ともいと、住友銀行の設立者〕さんに会ってそのことを話すと、吉左衛門さんは温厚篤実の人だから「それは何か不満のことでもあってのことか。ひょっとして月給が不足であるというのか。いずれにしてもあなたの満足するように取りはからうから、いま一度考え直してくれ」と、まことに情け深いことを言われるので、瀧沢君はせっかく懐にして行った辞表を差し出すわけにいかず、そのまま東京に帰ってきた。すると私は「なに構わぬ、辞表は郵便書留で送ってやれ」と瀧沢君を励まして、とうとうその通り実行し、いよいよ「丸吉」という屋号で仲買店を開業した。
▼十分間に東鉄一万三千株を買い占める
かくの如くして、私は瀧沢君によって機関仲買を得たので、勇気一層を増し、ここから先は縦横無尽に戦った。相変わらず買いの一方である。しかも、私の計画は着々と功を奏して、鈴木久五郎はほとんど天下に敵なしという勢いである。このとき一番多く買ったのは東京鉄道で、それは三十八年の七月である。当時の運賃は三銭均一であった。それが一週間ばかり後に一銭値上げになるということを、兄がある先輩から聞き込んだので、「いくらでも買えるだけ買え」と瀧沢君に号令をかけた。すると、ひと場所――たった十分ばかりのあいだに一万三千株を買った。相場は六十九円から七十円くらいであった。これまでも買占めをした人はたくさんあるが、ひと場所でざっと一万三千株買ったというのは、取引所開設以来のことであるそうだ。三井が炭坑株の買占めをしたときでさえ、前場で千株、後場で千株というふうに買ったのであった。
いくら「たくさん買え」と行っても、五千株か七千株であろうと思っていたら、さて買い出すと、あっちからも『ヤリ』、こっちからも『ヤリ』と、売り手は雲のごとく次々現れて、瞬く間に一万三千株を買ってしまったのである。〔相場用語で、ヤリ=売る、カイ=買う、という意思表示〕
私はそのことを知らずに自宅で朝寝をしていると、瀧沢君から「鎧橋わきの吾妻亭〔西洋料理屋〕まで至急きてくれ」という電話がかかってきた。行ってみると瀧沢君は、「誠に申し訳ないから辞職します」と言う。突然のことで私は驚いた。「どういうわけだ」と聞くと、「委細は兄さんにお話してあるから、兄さんから聞いてくれ」と言う。それで兄に聞くと、兄の言うには「おれも悪かった。いくらでも買えと言ったら、買いも買ったり、一万三千株買ってしまって、証拠金だけでも四、五万円は要る。証拠金の四、五万は何でもないとしても、もし仲買人一同に睨まれようものなら、叩き殺されてしまう。連合して売り崩されて今日も十円安、明日も十円安と来ようものなら、到底立つ瀬がない。あまりに深入りして面目がないから辞職しますと瀧沢君が言うのだ」とのことである。
そこで私が瀧沢君に言った。「買ってしまったものは後で何と言っても仕方が無い。しかし辞職するのは武士道ではない。昔の武士は死んでしまえば全ての罪が消えるように思っていたが、それは間違っている。失敗したらしたで、第二の計画を立てるのが本当の武士道である。君の失敗はとがめない。しかしその失敗を回復する道を講じるのが君の責任である。ナーニ、これくらいの後始末ができぬものか。ナポレオンは『出来ぬということは愚者の字引に見よ』と言った。我々が愚者でないとすれば、一致協力して適当なる善後策を講じようではないか」と激励して、私はさっそくその運動にとりかかった。
すると、三井と十五(銀行)で、再来月(九月)になれば四千株まで引き取ってくれるという。つまり、つごう八千株の引受者ができた。あと五千株くらいはどうにでもなると思ったから、ここ一番私の腹にたたみ込んでおいて、兄と瀧沢君とには「一万三千株を全部引き受けてくれる者がいたから安心なさい」と言った。このようにして機敏に戦闘準備を整え、後場の景気いかがと見れば、幸運なるかな、五十銭高ときている。
▼一挙に二十七万円を儲ける
ところが、このことが思いがけず諸新聞の注意を惹いて、翌日の記事に、「昨日、丸吉の店で東鉄の買占めをしたのは、村井〔村井吉兵衛、煙草王〕筋であるらしい」と書いているのもあれば「横浜の西洋人であるらしい」と書いているのもある。あるいはまた「金持ち筋の思惑である」とか諸説紛々としているが、いずれも的を外れている。
しかし、ここにただ一つ、確実な報道をした新聞がある。それは外でもない『中外商業新報』〔現在の日経新聞〕である。「あれは村井でもなければ西洋人でもない、確かに鈴木久五郎一派である」と、はっきり書いている。こうまでくるとさすがに中外商業はえらい。誰が機密を漏らしたのかは未だに分からぬが、とにかく、世評紛々たるなかで独り報道を誤らなかったのはさすがに商業専門の機関新聞である。私は、何にもならないことだけれども、この一事に対して少なからず中外商業に敬意を表して、その記事を切り抜いて保存してある。
それはともかく、我々はこの記事を見て少なからず狼狽した。「こうやって中外商業によって我々の行為が明白に伝えられた以上は、必ず仲買から逆襲を受けるに相違ない」と憂慮していたが、ものごとは案ずるよりは産むが易いもので、仲買らはだれ一人、反抗的態度をとらなかった。「これは運賃値上げのことをいち早く知ってやったことに違いない。運賃が一銭上がれば一ヶ月に八千円、一年に八、九万円の増収になる」ということで、買い方は方々から現れて、その二週間後に運賃値上げのことが発表されたときには八十七円という高値をつけた。それで我々は、実株を受け取る必要がなくなったので切って〔売り抜けて〕しまい、わずか二十四、五日のあいだに一挙に二十七、八万円を勝ち得た。
▼東株〔東京株式取引所。取引所自体も株式会社であり、その株が売買された〕の買占め
東鉄の買占めにはみごと凱歌を奏したので、それからさらに東株の買占めにかかった。東鉄の買占めは一時的な利益を争ったにすぎないが、この東株の買占めについては大いに理由がある。
一度でも足を取引所に運んだ者は、その家屋が狭隘で空気が腐敗しているのに眉を顰〔ひそ〕めざるをえないだろう。あの狭い『場』に人がいっぱいに入り組んで取引するのは、衛生上はなはだ宜しくない。とくに夏になると一層ひどい。そこでこれを改築して、空気の流通をよくし、夏などは打ち水をして香水の匂いくらいするようにしておかねばならぬ。聞く所によれば、進歩した外国の取引所では、その門前に自動表示器とかいうものがあって、ちょっとボタンを押すと、出来た相場〔売買が成立した値段〕がたちどころにその表示器に現れる。あるいはまた、この表示器を取り付けておく仲買店は、居ながらにして時々刻々の相場を知ることができるそうである。わが取引所も、このような構造にしたい。
それから、資本金を増したい。当時、取引所の資本金は四百万円、払い込みは二百五十万円に過ぎなかった。このような小額の資本金をもつ取引所が、はたして大取引の責任を負えるのかどうか。現に我々は、四百万円、五百万円の大取引をするたびに、少なからず取引所を危ぶんでいる。我々ごときがすでにそうだとすれば、ましてや外国人ならなおさらだ。将来、外国の仲買人と連絡をつけ、日本の株券を外国に売り出すなどということは、思いも寄らぬことである。「これは増資をしなければならぬ」ということで、買占めにかかったのである。
そうして我々一派でもすでに一万五千株、過半数以上を買い占めた。それからさらに取引所の株主有志を糾合して「丙午会(へいごかい)」というのを作った。ちょうど午(うま)の年に作ったから丙午会と名付けたのである。会員は二十七名であった。この丙午会で、取引所の株金〔株式に対する出資金〕を従来の三倍、すなわち一千二百万円に増資することに決議した。そのとき、岡本銀行の岡本善七氏と、通商銀行の籾山半三郎氏とが反対した。その反対の理由は「今は株式市場は非常に景気がよいけれども、今後かならず反動がくる。そのさい増資をしたせいで著しく配当が減じては困る。我々は日清戦争後のときに苦い経験を嘗めている。一時的な景気に浮かれて増資するのは早計の謗〔そし〕りを免れぬ」と言うのである。
そこで私は言った。「それはあなた方の頭が古い。日露戦争は日本開闢以来の戦争である。この戦争によって日本の偉いことが初めて世界に紹介されたのである。なるほど日本は日清戦争に勝った。けれども相手は支那である。列強は、日本が勝つのが当然だと思っていた。これとは違って、このたびは世界の最強国と称されるロシアに勝ったのである。同じ勝つでも勝った値打ちが違う。この戦勝のおかげで、日英同盟はますます強固となる。それと同時に、日仏同盟もできるかもしれん。日米協約もできるかもしれん。その結果、必ずフランスの資本が入ってくるだろう。アメリカの資本が入ってくるだろう。しかも彼らは、資本金が四百万円で払込みが僅か二百五十万円のわが取引所を見て、いかなる感を懐〔いだ〕くか。日露戦争後の日本は世界の日本である。日本がすでに世界的となれば、取引所もやはり世界的に拡張せねばならぬ。つまり今日は事情が違う。失礼ながらあなたたちの頭は古い。そのような古い頭をもって反対されては困る。あくまで反対されるなら脱会してもらいたい。脱会せぬなら、我々はあなた方二人のために丙午会の大勢を動かすわけに行かぬから、我々の方から除名する」と私が息巻く。「マァ喧嘩づくでは困る」と言って仲裁する者がいたので、会員一人一人について賛否を糺〔ただ〕すことにした。すると一同は賛成だという。結局、岡本・籾山の両氏も無理往生に賛成する事になって、ここに満場一致をもって増資案を可決し、取引所の理事長、中野武営〔なかの たけなか〕氏のもとに談判に行った。
我々はいきなり中野氏に「あなたは現在の取引所にご満足ですか」と問うと、「いや決して満足してはおらぬ」との答えである。「それなら一つ改革しましょう」と言って我々の抱負を語ると、「いかにもお説の通りである」と中野氏は同意する。そこで改革案は我々に一任することとなり、調査会というのを作って、私の兄がその会長となって調査に従事し、その結果、総会を開いて、ついに我々の希望どおり一千二百万円に増資することにした。
▼製糖会社の乗っ取り〔日本最大の製糖会社であった日糖=日本精製糖株式会社を、その幹部が鈴久と共謀して社長を追い出し、乗っ取った事件〕
鈴木久五郎のことを、世間が、単純な相場師とみなしているなら、これは少なくとも鈴木久五郎の半面を誤解している。これ〔東鉄や東株の買占め〕よりも以前に、私が製糖株を買い込んで大株主となったのも、やはり事業改良の趣旨から出たものなのだ。
私が二十六歳のときであったと思う。〔明治〕三十五年の議会に、「砂糖に重税をかけろ」という主張が出てきた。そのとき〔日糖社長の〕鈴木藤三郎君〔日本製糖業の父、発明王、実業家〕が反対説を述べて世に問うた。そしてそのとき私は、直接に鈴木藤三郎君からその理由を聞いた。「いま日本における砂糖の消費額は、なんと四億万斤〔一斤=600グラム〕だ。そのうち日本内地の製糖会社で清算する砂糖はいくらあるかといえば、実に少量である。日本の精糖業の前途は洋々たるものであると同時に、日本の精糖業はいまだ幼稚の域にある。この幼稚の域にある砂糖に重税を課したら、精糖業は潰れてしまう」
私は鈴木藤三郎君のこういう説を聞いていた。それから、三十七年に上海に行った際、非常に広大な二つの会社を見た。「あれは何という会社だ」と友人に聞くと、「あれこそ有名なるジャーディン・マジソンと、バターフィールド・スワイヤーという製糖会社である」と言う。そして「これらの会社が日本に砂糖を売り込んで、ともすると日本の製糖会社を圧倒しようとするのだ」と友人は私に説明した。私は、前に聞いた鈴木君の説が、いかにも道理のあることを痛切に感じた。そこで上海から帰国するとすぐに製糖株を買い進み、一万二千株も手に入れたのであった。
すると磯村音介〔日精の支配人〕が私を訪れてきて言った。「どうだ、日本の精製糖業の統一を図ろうではないか。内地の会社が互いに競争していては潰れてしまう。我々は同胞相食むという愚を去って、大合同を企て、外国の会社と戦争しようじゃないか」と言う。「それは私も大賛成だ」と意気投合して、鈴木藤三郎君(社長)のところへ談判に行った。すると鈴木社長は、「お説は同意するが、時期がまだ早い。いまに大阪の製糖会社は消滅してしまうから、それまで待て」と言って聞かない。しかし我々は、「そんな気の長いことは言ってられない」ということで株主の委任状を集めてみると、過半数以上が集まった。そこで「株も大丈夫だ。社長が固執して動かないならば、強制施行をやろう」と、不信任状を懐にして総会に臨んだ。ところが、色々ゴタゴタして、一時に開かれるはずの総会が四時になってようやく開かれた。それと同時に、現重役が総辞職をした。彼らは、大勢はすでに動かすことができないと見て、早くもここに覚悟をしたものらしい。
そこで代わりに立ったのが、専務取締役に磯村音介君、常務取締役に秋山一裕〔日精の参事。磯村と共謀〕君である。中村清蔵〔鈴久の奉公した「上清」の主人〕君が平取締として入り、監査役には私と、砂糖問屋を代表した後藤長兵衛君とであった。これが三十九年の五月である。それから六、七、八、九の四ヶ月を経て、大阪製糖会社と合併することを決め、十二月の総会でついに合併を結了した。そのとき「重役はあまり若い者ばかりではいけない」ということで、澁澤男爵〔渋沢栄一、日本資本主義の父〕を相談役として、酒匂常明〔さこう じょめい、農学者、官僚〕氏を社長となし、平取締に渡辺福三郎〔横浜の実業家〕、監査役に藤本清兵衛〔のちに大和証券となる藤本ビルブローカー創業者〕などが入ってきたのである。
▼鐘紡の買占め事件
東京株式取引所株の買占めは首尾よく目的を達し、製糖会社も理想の八割は実現した。さて、この次は何の統一を図ろうか、と考えた末に、ふと胸に浮かんだのは紡績業である。日本には紡績会社がたくさんある。鐘ヶ淵紡績、富士紡績、東京紡績、この三つが東京の三大紡績会社である。それから関西に行くと、摂津紡績、大阪紡績、名古屋紡績、三重紡績、その他いろいろな会社がある。
これほど多くの紡績会社があるにもかかわらず、その製品を海外に輸出しているのは、ほとんど鐘紡一社にすぎず、その他はことごとく内地で同士討ちをしている。同士討ちは日本の殖産興業を疲弊させるだけである。これを統一して、もっぱら販路を海外に求め、清国〔中国〕市場において外国品と競争するのが男子の事業であって、また我らの急務である。我々はここで、もっとも強固な「鐘紡」を中心として他の小さい会社を併呑することで、我々の理想を貫徹しよう、ということで、鐘紡の株を買い出すと、これが図らずも、呉錦堂〔ご きんどう、神戸の華商〕と一大戦争を開く原因になった。
というのも、不思議で仕方がないことに、当時は株式全体が騰貴していたのにもかかわらず、鐘紡の株のみが百三十円から百四十円に居座って動かないのである。どういうわけかと調べてみると、それは神戸にいる呉錦堂というチャンチャン〔中国人に対する当時の蔑称〕が一人で鐘紡を四万株持っていて、高くなれば売り崩し、安くなれば買い戻すせいであって、そのようにして彼は鐘紡株の相場を一手に左右している。しかも彼の背後には、鐘ヶ淵紡績会社の実権者にして、紡績界のオーソリティーたる武藤山治〔むとう さんじ、鐘紡の中興の祖〕という豪傑が控えているので、彼は実に驚くべき大勢力を持っている。
あるとき、呉錦堂が馬車に乗って、東京の取引所を見に来たことがあった。そのときの株屋連中の騒ぎはたいへんなもので、「サア呉錦堂が来た、売るか買うか、売れば安いし買えば高い。どうなることか」と七十軒の仲買が、彼を見て震えているのである。
調査の結果、こういうことがわかったので、私は奮然として立った。「そいつはすこぶる面白い。一つ戦ってみよう。なんの、相手は高の知れたチャンチャンである。一人のチャンチャンを恐れて東京の七十軒以上の仲買が何もできないでいるとは、あまりに意気地のない話である。やっつけろ」と、強敵を発見して私の勇気はさらに百倍した。
しかし、用意はあくまで周到なることを要する。私ら兄弟だけではいささか心もとない感がないでもない。といっても、途中で裏切りをするような者を味方にしたら却って破滅のもととなるので、私と富倉林蔵〔とみくら りんぞう、株式仲買人〕とが主となり、これに中村清蔵君、中島興平(なかじま よへい)君なども加え、少数だが堅い同盟を作った。東京と大阪の両方で買う事にして、東京は瀧沢の店に、大阪は広崎の店に注文し、きょう私が買えば富倉が休み、明日私が休めば富倉が買う、というように交代に買って両方一度に潰れないように用心し、いよいよ怪傑呉錦堂に戦を挑んだ。
◎呉錦堂との激戦
かくの如く、充分に策戦計画を整えて、まず百四十五円くらいから買い出して、百五十六円から百六十円に競り上げ、百七十円にまで買い煽ると、ついに呉錦堂の気付くところとなった。予想どおり、例のやりかたで売ってくる。すると、百七十円まで上がった相場がたちまちにして百五十五円に墜ちる。「ナンノ」という意気でさらに買い煽って百七十円にのぼせる。と、たちまちまた百六十円台に落とされる。買い上げると引き落とされる。また買い上げるとまた引き落とされる。このように一上一下、たがいに火花を散らして戦うこと二週間以上、とうとう百九十五円まで買い煽ると、またまた百九十円まで引き落とされた。
そこで私は考えた。「これはなかなか尋常一様の敵ではない。うっかりするとやられる。我々は過去二年間、鈴木家の興廃を賭して惨憺たる苦心を経た結果、ようやくここまでこぎ着けたのに、いまこの戦に負けては、いわゆる『九仭の功を一簣に欠く〔最後の少しの失敗で長い間の努力が無駄になる〕』だ。深く思慮を廻さねばならぬ」と思い、またまた例の花月花壇〔向島の大規模観光施設、遊園地と西洋料理。明治39年に鈴久が別荘として買収〕に行って同志と相談した。相談の結果は、「実株を受け取って、我々の基礎が強固であることを敵に示すしかない」ということになった。
ところが、これを銀行に交渉すると、三井(銀行)でも十五(銀行)でも、「平に御免を蒙る」と言って我々に金を貸してくれない。それなのに、このときただ独り、我輩を信じて金を貸してくれたのは安田銀行である。それは前々号において『私の失敗時代の回顧と楽天主義』という題下で話したから再び述べないが、ここにおいて我々は勇気一倍を加え、さらに買って買って買い抜いた。
すると呉錦堂の方でも大いに弱り出し、ついに三菱にすがって救済を求めた。なにしろ呉錦堂は百三十円台から売り出しているのだから、巨額の追敷〔追加証拠金〕に攻められている。彼は、株式や不動産は多く持っているが、現金は百万円くらいしか持っていない。さすがの彼も三菱に泣きついて、その救済を求めたのである。泣き付かれて三菱はさっそく承諾したが、「売った株は一つ残らず渡さねばならぬ」という条件である。「はいはい仰る通り、いかようにもいたしますから」と懇願して、こうして彼は三菱の後援を得てさらに我々と対抗した。
そこで戦はますます激しくなる。いよいよ猛烈なる悪戦苦闘を続けた。
しかし、幸いにして我々は始終優勢な地位に立ち、とうとう二百円を踏み切って二百三円にまで買い上げた。そこで世間では「日本は二百三高地を占領して勝った。二百三高地と二百三円、これが縁起がよいことである。鈴久の方が勝つに相違ない」と言って、早くも我々の前途を祝してくれた。はたしてその通り、我々はこの戦においては呉錦堂に勝ったが、天いまだ鈴久に幸いせず、その後の暴落に際してこれが我々の致命傷となり、没落したのは遺憾の極みである。
◎激戦の結末
二百三円まで買い上げると、村井銀行〔たばこ王・村井吉兵衛が設立した銀行〕の酒井静雄君が、出張先の大阪から手紙をよこした。「京都の土産に面白いものがあるから、いずれ近日中に帰郷の上、お目にかける」と書いてある。それから二、三日経って、「明日午前九時新橋着」という電報がきた。迎えに行くと、「君に話があるから」というので、二人で新喜楽〔築地の料亭〕に行った。
私が「面白い土産とはどんな土産だ」と聞くと、「それは、とにかく君に熟考をしてもらいたい大問題がある。古来、両雄並び立たず〔二人の英雄は共存できない〕という。君はいま、呉錦堂と火花を散らして戦っているが、いずれ、どちらか傷つくに相違ない。これは天下のために実に惜しむべきことである。呉錦堂は関西における成功者の一人である。君も関東における成功者の一人である。どちらが傷ついてもいけない。どうにかして丸く和睦をする気はないか」と言う。
そこで私は言った。「和睦する気はある。もともとこちらは戦を好むのではない。鐘紡を中心として、紡績業の統一を図るというのが僕の目的で、それにしては鐘紡の現在の資本金、五百五十万円では足らぬ。これを倍にして千百万円に増資し、その増資金をもって小さな紡績会社を併呑したいというのが、そもそも呉錦堂と戦を開くことになった理由である。千百万円に増資し、そしていま鐘紡はだいぶ儲かっているそうだから、配当を二割五分にして、我々一派から重役を一人入れてくれさえすれば、僕はいつでも和睦する」と言うと、「それならちょっと待ってくれ」と言って立って行った。
酒井君は、前もって部屋に待たせておいた三井銀行の神戸支店長、小野友次郎(おの ともじろう)君を連れてきて私に紹介した。そこでまた小野君といろいろ話すと、小野君は「それは容易ならぬことである。益田(ますだ)さん(三井同族会監理部副部長)、朝吹さん(鐘紡専務取締役)に相談した上でなければ返事は出来ない」と言って、その日はそれだけにして別れた。
別れ際に酒井君が言うには、「とにかくこの話が落着するまで株を買ってくれては困る。このうえ買い煽られては呉錦堂が死んでしまう。いまのところ現状維持にして貰いたい」と言うから、「よろしい承知した。そのかわり呉錦堂も売っては困る」。「それは決してさせない」ということで、後日の再会を期して別れた。
それからいろいろ交渉した結果、朝吹さんが言うには、「あなたの要求どおり、資本金は倍に致しましょう。配当も増しましょう。ただし二割五分では困るから、二割で我慢してください。それからあなたは大株主であるから、重役を入れるか入れないかは、もとよりあなたのお考えしだいだが、しかし私どもの立場としては、十数年来の歴史を有する鐘紡を、一挙にあなたに乗っ取られたとなっては、三井家の顔にかかわる。これは徳義上、忍んでもらいたい。その代わり、社長の三井養之助をはじめ私ども重役一同総辞職をするから」と言うのである。
私は、「長い歴史を有する三井に対して、とんだ要求を致しまして恐縮の至りです。私はただ、私の代表者として重役を一人入れていただければそれで満足なのです」と、ひたすら、総辞職の必要はないことを勧告したけれども、朝吹さんは「私たちの腕がないのと、徳がないので、このような失態を惹き起こしたのであるから、責任上ひとまず総辞職をいたします」と言うので、談判は終わりとなった。
そこで時の重役一同は辞職し、資本金を一千百万円、配当を二割にして、日比谷平左衛門〔ひびや へいざえもん、日本紡績界の巨人、鐘紡設立にもかかわる〕氏が新たに社長となった。これにて株式界空前の活劇と称された、呉錦堂と私との戦争は終わりを告げたわけである。
休戦中、鐘紡の株は二百九十五円にまで騰貴した。このとき私の財産を清算すれば、一千万円以上に達していた。私には大隈伯の忠告を容れる明がなく、栄華は槿花一朝〔むくげの花が朝咲いて夕にしぼむこと〕、夢のように果敢ない最後を遂げたのは、すでに前号に述べたから改めて贅せぬ。
〔おわり〕
*呉錦堂に対し蔑称を用いるなどしている箇所があるが、時代を鑑みそのままにした。なお、呉錦堂は日露戦争勃発前に軍債45万円を献納して中国人として始めて叙勲され、日本国籍も得ている。鈴久との戦いで破産するが、三菱銀行の融資で救われ、その後は実業に専念したという。
================================
【訳者(長谷川珈)より】
鈴久は、たんなる「相場師」であるには留まりませんでした。大株主としての力で企業の改革再編に乗り出し、事業家・資本家としても暴れまわったのです(その成否や良し悪しはともあれ)。当時、日本の基幹産業は繊維業。日本最大の企業であった「鐘紡」の実権を握ったとき、彼の栄光と資産は頂点に達しました。
その後の没落過程には、三編とも、ほとんど触れていませんね。鈴久が書こうとしなかったのか、(聞き書き記事だとすれば)記者が遠慮したのか。それはわかりませんが、失敗についてぐずぐず言わないところが、鈴久の勝負師らしい潔さかもしれません。
鈴久の告白記は以上です。翻訳(というほどの作業ではありませんが)しつつ読み返しましたが、何度読んでも面白い。
国会図書館での検索では、これら以外に、鈴久自身による文書は見つかりませんでした。ただ、私の検索がへたくそだっただけかもしれません。鈴久の全盛期には、その行状が毎日のように新聞紙面を賑わしたといいますし、破産した後も衆議院議員を一期務めたくらいですから、彼自身による文書や聞き書きなどは、他にも存在するはずです。また面白いものが見つかれば掲載してみたいものです。
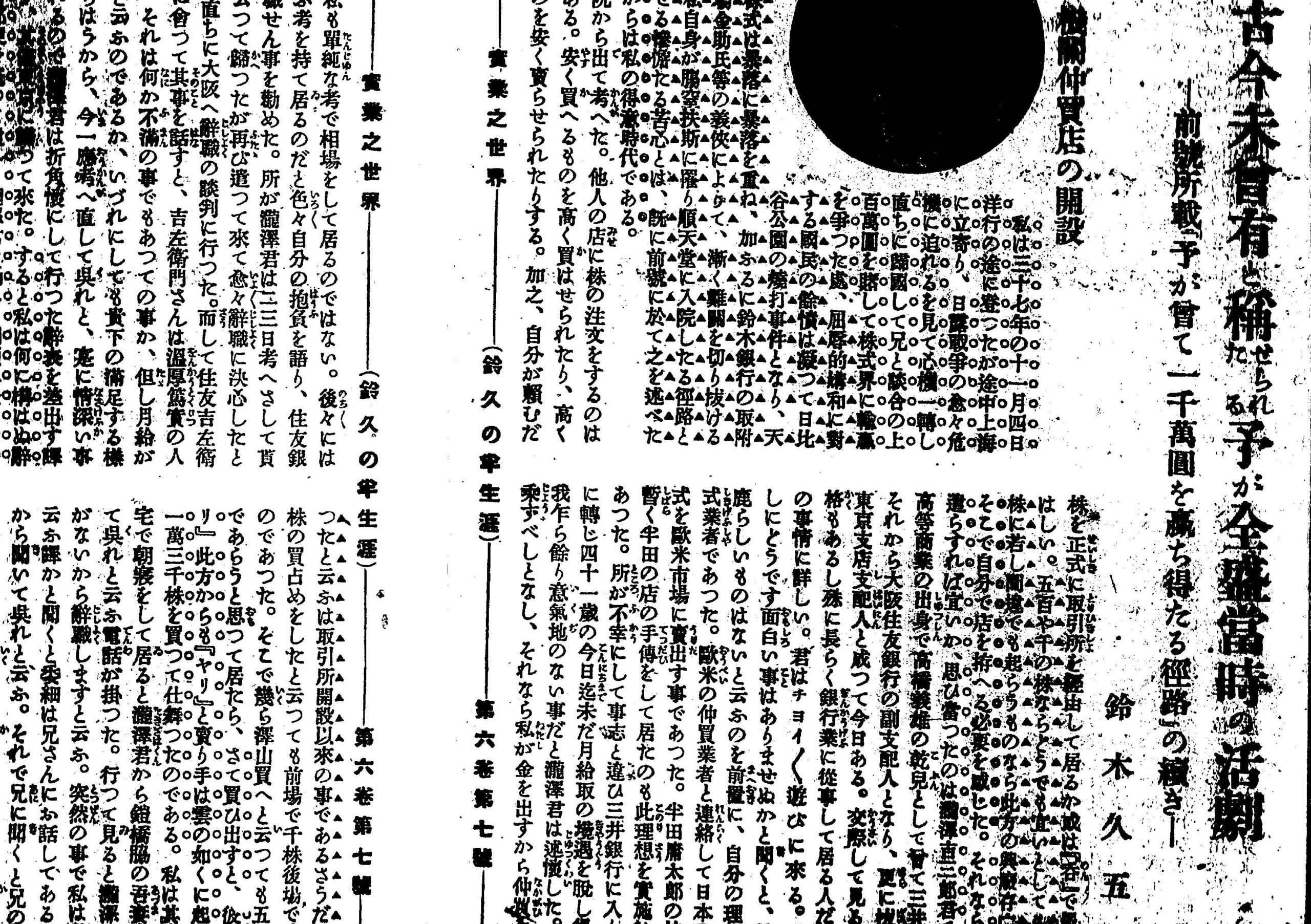


コメント